-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
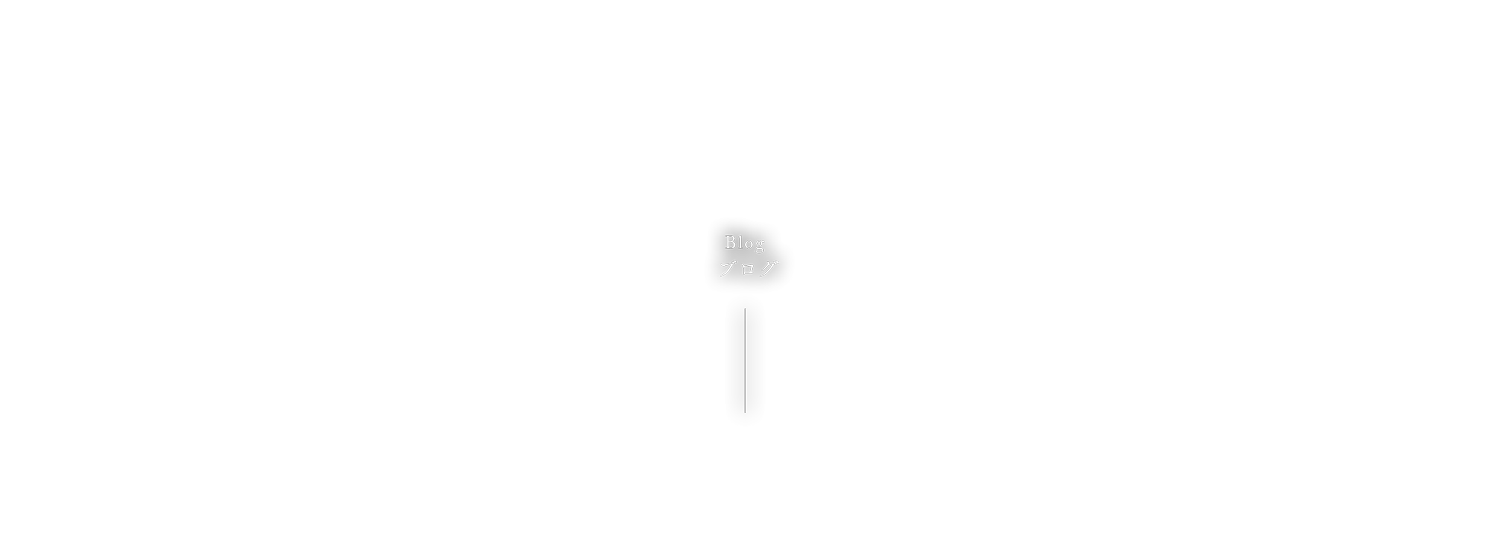
皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part14~
ということで、茶樹の育成において特に注意すべきポイントや手入れの方法を、時期別・目的別に深掘りしてご紹介します。
お茶の品質は、自然条件と栽培技術の融合で決まります。中でも、農家の“気づき”と“手入れ”の積み重ねが、香り・色・味を引き出す鍵です。
霜害防止:春の遅霜対策に防霜ファンや散水を活用
追肥のタイミング:芽出し肥は3月中旬~下旬に施す
芽の揃いを見る目:ばらつきがあれば整枝調整も検討
🌱 新芽の品質は「春にいかに守り育てたか」で決まります。
冬剪定(1月〜2月):強剪定で新芽更新を促進
夏剪定(7月〜8月):光合成効率向上・病害予防
浅刈りと深刈りの使い分け:年ごとに交互施行が理想
✂️ 樹形の乱れは収穫効率にも直結するため、計画的に管理。
春前の基肥(1~2月):芽出しの力をつける
追肥(4月~5月):一番茶後の樹勢回復
秋肥・冬肥(9~11月):来年の芽と根を育てる基盤
🍂 肥料の与え方一つで、葉の厚み・香り・苦渋味が変わります。
定期観察と発生傾向の記録
薬剤ローテーションによる耐性対策
防除カレンダーの活用(地域JA配布の防除表も参考)
🔍 葉の裏・新芽の先を毎日見る習慣が、不作を防ぎます。
かぶせ茶:摘採の10〜14日前から被覆
玉露:3週間以上の被覆が標準
黒い寒冷紗やワラを使って光合成を制限しテアニンを増やす
☂️ 被覆資材の管理(耐久性・透光率)も品質管理の一部です。
機械除草と人手による根切りの併用
梅雨・夏場の排水対策(高畝や側溝の整備)
💧 根にストレスをかけないための環境整備が健康な茶葉を育てます。
お茶農家の仕事は、一見同じ作業の繰り返しに見えて、毎日違う“茶の表情”を見分ける観察力と判断力が求められます。剪定、施肥、防除、被覆――これらすべてが“手をかけたお茶”の味わいにつながります。
“気づける農家”が、“選ばれるお茶”をつくるのです。
