-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
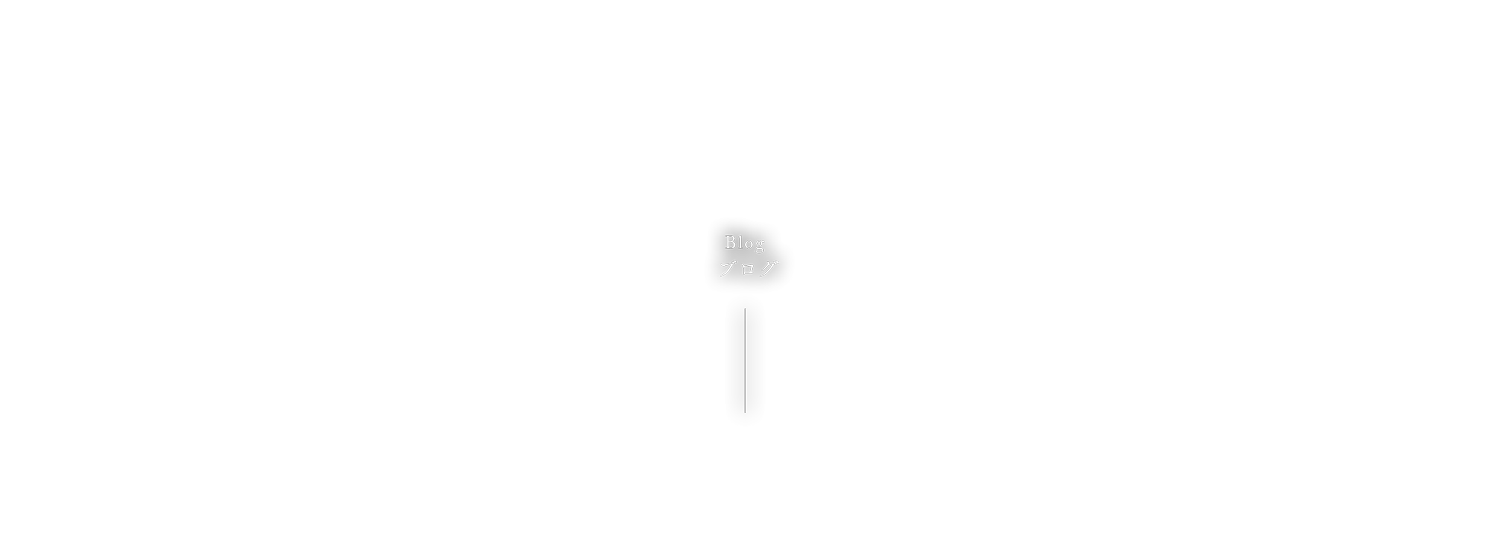
皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part25~
11月のお茶農家は、比較的落ち着いた時期と思われがちです。
しかし実際には 「来年の新茶の品質を決める一番大事な時期」 と言っても過言ではありません。
立冬を迎え、朝晩は10℃以下になる日も増え、茶園は冬の眠りに向けてゆっくりと準備を始めています❄️
そんな11月の茶園では、秋冬仕立て、土づくり、病害虫の最終チェック、霜対策準備など、多くの重要作業が進められています。
ここでは、11月の茶園管理がなぜ大切なのか、どんな作業が行われるのか、来年の品質にどう影響するのかを、専門的かつ分かりやすく深掘りします✨
目次
11月はお茶の木にとって “冬支度の段階” です。
日照時間が短くなる
朝露が増える
気温差が大きくなる
土壌温度が下がり始める
茶株の成長が緩やかになる
つまり「今の管理=来春に出る芽の質を左右する」ということ。
お茶農家の11月作業は、春を見据えた長期的な視点で進みます✨
11月の茶園の主役作業といえば、 “秋冬仕立て”。
これは来年の一番茶の芽が出やすいよう、枝葉を整える作業です。
放置すると
枝が込み合い、日当たりが悪くなる
新芽の出る位置がバラつく
収穫量が下がる
病気が発生しやすくなる
11月の段階で枝を整理しておくことで、
春の新芽の出る“スタートライン”が整います。
古い枝・枯れ枝の除去
混み合った枝を間引く
日当たりを良くするための上部調整
刈り落としで株を均一に仕上げる
この作業は技術の差が大きく出る部分。
数ミリの高さが翌春の芽出しに影響することもあるため、かなり繊細な仕立てが求められます✨
11月は肥料を与える“秋肥”の時期でもあります。
秋に肥料を与えることで
冬越しに必要な栄養を蓄える
根の生育を促し、春の芽の力を強くする
茶樹の活性を保つ
深根化による基盤作り
特に有機肥料を使う場合、分解に時間がかかるため、春に効かせるためには“11月”がベストです。
有機肥料(油かす・鶏糞・ぼかし肥など)
粒状化成肥料
堆肥のすき込み
土壌改良資材(ゼオライト・苦土石灰)
土壌分析に基づき、窒素・リン酸・カリの配合を調整する農家も増えています。
繁忙期と比べて発生は少ないものの、11月は“最後の見回り”の時期。
特に
チャノホソガ
カンザワハダニ
黄化現象
うどんこ病の初期症状
これらを放置すると、越冬して翌年に被害が広がります。
12月に入ると、地域によっては霜が降り始めます。
霜害は新芽が出る翌春に致命的な被害を与えるため、11月から準備を開始します。
防霜ファンの点検
給油・稼働試験
温度センサーの確認
茶園の風通しの調整
草刈りで地温低下を防ぐ
防霜ファンは、一番茶の品質を守る“茶園の守護神”とも言われる大切な設備です❄️
畝間の草刈り
排水路の整備
土の盛り直し
茶園周囲の片付け
冬の害獣対策
特に11月は“排水”が重要。
冬に雨が多い地域では、土壌が過湿状態になると根腐れが起きやすくなります。
お茶農家にとって11月は「静かだが最も重要な準備期間」。
まだ寒さの本番ではなく、茶の木も冬眠前の余力があるので、
株の整え
根の伸長
土壌改良
病気対策
が効率よく行えるのです。
人で言えば、冬に備える体力作り・ストレッチのような時期といえます
11月の茶園は、一見何も変化がないように見えて、裏では“来年の春の準備”が進んでいる大切な時期です。
秋冬仕立て
土づくり
病害虫チェック
防霜準備
排水改善
これらの積み重ねが、来年の一番茶の香り・うま味・品質につながります。
丁寧に整えた茶園は、春に必ず応えてくれる──
それが、お茶農家の11月の本質なのです✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part24~
「選ばれ続ける」ためのブランド・商品・体験・環境・人の話。価格競争ではなく、価値競争へ。6次化(加工)×観光×デジタルを組み合わせ、ファンと一緒に育つ茶園を目指しましょう。
目次
ストーリー軸:品種の来歴、標高、朝霧、被覆、家族の役割。
科学の裏付け:アミノ酸・カテキン・カフェイン等の簡易分析(外注OK)→味覚の理由を数値で示す。
写真と言葉:茶畑の陰影・雲海・露を切り取る。コピーは五感+具体で。「湯冷まし50℃、とろり甘旨」
フラッグシップ:単一畑・単一品種・年ごとにロット番号。限定性でファン化。
デイリー:ブレンドで味の安定を提供。定期便の軸に。
体験型:水出しボトルキット・ラテベース・茶スイーツ素材(抹茶・粉末ほうじ茶)。
ギフト:季節しおり・淹れ方カード・ペアリング案を同梱で“説明いらず”。
正面:品種/火入れ強弱/旨・渋・香のレーダー。
側面:抽出レシピ(温度・時間・湯量・二煎目)。
背面:畑座標・標高・収穫期・被覆の有無・ロットQR。
素材:アルミ蒸着+チャックで鮮度キープ。30g/80g/200gの使い切り設計。
小型焙煎機×二段火:低温で甘香→仕上げに高温で香り立ち。
真空パック・脱酸素剤:火入れ後の酸化スパイクを抑える。
粉末化:**微粒粉砕(超微粉)**は耐湿管理が命。シリカゲル+窒素置換で固結回避。
委託加工を賢く併用:品質基準とロット管理を明記したSLAを締結
新茶手摘み体験(5月):摘んで→蒸して→手揉み→試飲。オリジナル缶に封入してお土産へ。
朝もや茶会:日の出&雲海×一煎。写真コンテンツとしても最強
焙煎ワークショップ:自分の火入れでマイブレンドづくり。
カフェ併設:茶プリン・ほうじラテ・抹茶ソフトで客単価UP
安全配慮:刈払機・蒸し釜周辺は立入線/保険/熱中症対策を徹底
オンライン茶会:月1回、同じロットを飲みながら味を言語化。
茶畑オーナー制度:名前入り札&収穫ボーナス。農繁期ボランティア受け入れで人手も確保。
レビューの可視化:悪い声も改善実績とセットで公開=信頼貯金
お菓子屋さん:抹茶/ほうじ粉末の粒度・香気を試作セットで提案。
カフェ:水出し濃縮×ソーダ、ほうじ×ミルクフォームのドリンク開発。
酒蔵:緑茶酒・ほうじ茶梅酒でコラボ。季節限定はSNSで拡散しやすい
被覆資材の再利用率、ボイラ燃料の切替(LP→電化/木質)、製品当たりCO₂を開示。
生物多様性:畦の草花ベルトで天敵昆虫を呼ぶ。フェロモントラップで農薬低減。
雨水利用・太陽光:水出しラインのチラー電力を再エネに。
茶殻アップサイクル:消臭材・コンポスト・染色に活用♻️
猛暑&少雨:点滴灌水+マルチングで葉温を下げ、苦渋みの暴発を抑制。
春の遅霜:防霜ファン+散水氷結の複合。SMS一斉アラートで緊急招集
炭疽病・輪斑病:風通し(剪枝)と発病葉の早期除去。
人材:マニュアル動画化/技能マトリクスで“属人化”を溶かす。繁忙期は地域×学生バイトのハイブリッド。
EC:定期便(毎月/隔月)、季節限定、送料無料ライン、レビュー特典。
実店舗:試飲→即決の導線。0.5g×3種の飲み比べで「違いがわかる」を演出。
同梱物:淹れ方カード・ペアリング表・畑だよりで“箱を開けた瞬間から茶会”。
写真:逆光で透ける茶葉、注ぎ初めの“黄金の糸”。光の演出が命
歩留まり(荒茶→仕上げ%)、再焙煎率、返品率、鮮度在庫日数、定期便継続率。
イベントKPI:体験参加→EC登録→2ヶ月後購入の転換率。
CXスコア:「また買う/人に勧めたい」をアンケで数値化。改善はひとつずつ
打ち手:単一畑ロット化/火入れ二段化/水出しキット化/朝もや茶会/CO₂表示。
結果:定期便継続率**+18pt**、ギフト客単価**+27%、来園→EC登録+42%**。
学び:体験→言語化→データの循環がブランドを強くする。
小さな茶園でも、大きな物語を育てられます。鍵は、畑のリアルと科学の言葉、体験の楽しさと環境の誠実さを一本に束ねること。今日の一歩は、製品ラベルに“抽出レシピ&ロットQR”を足すだけでもOK。あなたのお茶は、きっともっと“語られる味”になります。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part23~
茶樹の声に耳を澄まし、天気と対話し、工程を科学する。そんな“丁寧な当たり前”の積み重ねが、湯飲み一杯の感動に変わります。今日は、圃場管理→摘採→製茶→仕上げ→販売まで、一気通貫の“勝ち筋”を解説します。✨
目次
園地の向き(アスペクト):東向きは朝露が早く乾き病気リスク低減。北風の当たり具合で芽伸びが変わる。
土作り:pH5.0〜5.6目安。**完熟堆肥+有機質(菜種粕・魚粉)**で団粒構造を育て、**根の“呼吸”**を守る。EC(電気伝導度)で施肥過多を見える化
品種設計:早生(やぶきた)×中生(おくみどり)×晩生(さえあかり)でリスクと収穫負荷を分散。被覆適性や萎凋向きもあらかじめ想定。
かん水・排水:極端な乾燥は旨味(アミノ酸)↓、過湿は根痛み→黄化。点滴チューブ+土壌水分センサーで「与えすぎない勇気」
ミニTIP:苗の定植は南北畝で光を均等に。終日西日の強い畝は被覆ネットで葉温を抑え、渋みの暴発を防ぐ️
剪定:深刈りは更新、浅刈りは収量維持。2〜3年の設計でローテーション。
整枝:摘採面をフラットに保つ=均一蒸しの土台。波打ちは粉砕・粉がれの原因。
被覆(玉露・かぶせ茶):遮光率・期間で旨味の伸びが変わる。直掛け→本簾へ段階的に。葉色・香の“変調”を観察
基準:一芯二葉(早取りは旨味↑・香り繊細/遅取りは香り濃いが渋味↑)。
時間帯:朝露が切れてから。露付きは蒸しムラ&粉砕の元。
機械設定:回転数・刃当たり・コンベア角度で粉砕率が激変。**“葉が泣く音”**がしたら刃圧高すぎ
ロス対策:コンテナの通気・保冷。摘み置き加熱を防ぐため、30分以内搬入を厳守
蒸し:浅蒸し(香り立ち&透明感)/深蒸し(濃度&まろみ)。芽の硬さ×葉厚×葉温で秒数を微調整。蒸しすぎは青臭消失&粉増、不足は渋味尖り。
粗揉:揉みこみは細胞をほぐし水分均一化。風量と温度で乾燥速度の曲線を描くイメージ。
中揉:線条を整え、過乾燥を避けて内部水分を中心へ移動。
精揉:光沢を出し、形を締める。ここでの手離れ感は香味安定のサイン✨
乾燥:水分4〜5%目標。水分計の校正を月1回。乾きムラは火香の付き方を不安定に。
センサー活用:排気湿度・排気温のログ化で、蒸しから乾燥までの“香味カーブ”を見える化
篩い分け:針状・粉・茎などパーツごとに。欠点除去=味の解像度UP。
火入れ(焙煎):低温長時間→甘香(あまか)、高温短時間→香ばしさ。二段火で奥行きを作る。
合組(ブレンド):畑違い・ロット違いを狙いの味に寄せる職人技。味覚ボキャブラリー(旨味・渋味・滋味・火香・青香)をチームで共通化️
青臭の過剰:蒸し不足→蒸し秒+5〜10/眠り葉混入→選葉強化
渋味尖り:摘採遅れ/高温乾燥→火入れ温度↓+時間↑
にごり出汁:粉の混入→ふるい強化/深蒸し過多→蒸し温度見直し
吸湿臭:保管温湿度×包装。脱酸素・低温倉庫で鮮度キープ❄️
煎茶:70℃・1分→甘旨、85℃・30秒→香強。二煎目の最適化も提案。
玉露:50℃・2分で旨味の海。
ほうじ茶:95℃・30秒、ミルク割りのレシピカードを同梱
水出し:冷蔵3〜4時間。カフェイン控えめ訴求で夏の主役
生育モニタ:葉温・土壌水分・日射量をクラウドで。
CO₂見える化:ボイラ燃料・電力使用量を製品当たりで表示→環境値をブランドに。
トレーサビリティQR:畑・品種・蒸し秒・火入れ温度を開示=信頼の源泉
季節便(新茶・夏の水出し・秋の焙じ・冬の玄米茶)
ペアリング提案(和菓子・チーズ・チョコ)
ティーバッグは“美味しい”を証明:ドリップ式や三角メッシュで抽出性↑
SNS:蒸気の立つ動画・茶葉の手触り・湯呑みの音——五感を伝える
お茶は畑→工程→言葉→体験の総合芸術。畑で整え、工程で磨き、言葉で届け、体験で定着させる。今日からできる一歩は、蒸し〜乾燥の排気ログをとって“自園の香味カーブ”をつくること。来年の新茶、きっと別格になりますよ。✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part22~
湯呑み一杯の向こう側には、1年を通して続く畑の管理、短い収穫期の勝負、そして加工・販売という長い工程があります。近年、お茶農家の現場では、気候・人手・価格・規制など複数の波が同時に押し寄せ、従来のやり方だけでは乗り切れない局面が増えました。本稿では、日本の茶産地を想定しつつ、畑・工場・市場の3視点から課題を整理し、すぐに着手できる打ち手までまとめます。
目次
晩霜・春先の寒戻り:一番茶の芽吹きが早まるほど霜害のリスクが上がる。防霜ファンや散水、黒マルチなどへの投資負担が増加。
猛暑・干ばつ・豪雨:夏場の高温乾燥は樹勢を落とし、旨味成分の蓄積に影響。豪雨は土壌流亡や根傷み、排水不良を誘発。
収穫タイミングの難化:フェノロジー(生育リズム)の変動で「いつ摘むか」の決断が難しく、品質×歩留まりの最適点が読みにくい。
チャノミドリヒメヨコバイ、小さなハマキ類、カンザワハダニ…。高温化で世代回転が早まると防除回数が増え、耐性化リスクやコストが上昇。
有機・特別栽培では選べる資材が限られ、草生管理や天敵温存など**総合的病害虫管理(IPM)**の設計が不可欠に。
収穫は極端な繁忙の“瞬発型”。世帯内労働だけでは回せず、機械化・共同作業・外部人材の確保が必須。
高齢化で重労働の継続が難しい。摘採機・運搬・選別の動線を見直し、腰と肩への負担を“設計で”減らす必要。
化学肥料高騰や施肥制限で、有機質の回帰・土づくりに再び注目。
品種の多様化は品質の幅を広げる一方、最適な防除・摘採時期・被覆条件が畝ごとに違う難しさも。
蒸機・乾燥機を回す燃料・電力の高止まり。被覆(覆下)資材や網、防霜・防鳥のネットもコスト上昇。
省エネのための更新投資(インバータ化、断熱、熱回収)が必要でも、回収年数が長く資金繰りの壁に当たりやすい。
シングルオリジン、単品種、発酵茶や紅茶化など多品種少量のニーズ増。
ロット分け・トレース・在庫管理の手間が増し、**品質の“再現性”**を保つ運用が難しい。
HACCP 的な衛生管理、異物混入防止、残留農薬の**MRL(基準値)**対応。
海外輸出や大手取引では記録と証跡が求められ、紙台帳からの脱却が課題。
市場平均価格が伸び悩む一方、上物と下物の二極化が進行。
仕入先や流通の都合で、“良いもの”でも適正に評価されないケースが残る。
急須離れの一方、抹茶・ボトルティー・ティーカクテル・健康文脈など新しい入口は拡大。
ただし新カテゴリーは規格・衛生・表示の壁が高く、参入コストがネック。
農協・市場任せから、**直販・EC・観光(アグリツーリズム)**へ。
物語・写真・英語対応・配送・カスタマーサポートまで含めると、“農家の仕事”が増え続ける。
防霜の多層化:ファン+黒マルチ+簡易風除け、可搬温湿度ロガーで危険閾値を見える化。
IPM:フェロモントラップ、被覆下の湿度管理、茶園縁の草・樹種の選定で天敵温存。
土づくり:剪枝くずのチップ化・堆肥化、被覆作物(クローバー・ヘアリーベッチ)で有機物と保水を確保。
共同雇用プール(近隣数戸でのシェア)、摘採機の共同利用カレンダー。
収穫〜運搬の動線見直し(斜面にはモノレール・自走運搬車、集積点の固定化)。
学生・地域人材の短期アルバイトには、30分動画の作業eラーニング+現場チェックリストを準備。
熱回収・断熱・インバータで“燃やした熱を逃がさない”。
ロットID管理(QR)で生葉→荒茶→仕上げまで紐付け。単品種・単畝でも混乱しない台帳に。
小規模発酵ラインの試験スペースを確保し、紅茶・烏龍・発酵茶の**“二の矢”**を育てる。
シングルオリジンの設計:区画、品種、被覆日数、蒸しの強弱など**“違いの言語化”**。
ECの基本整備:淹れ方動画、写真(茶畑・製造・リーフ・水色・茶殻)、2分で強みが伝わる商品ページ。
観光・体験:新茶期の“摘採見学+製茶見学+試飲”、秋は“焙煎体験”。一次情報の提供はブランド力に直結。
法人向け:ボトルティー用の抽出適性、抹茶・粉末緑茶の粒度や溶解性などB2B規格表を用意。
共同機械リース・協同購入で初期費用を分散。
再エネ活用(屋根ソーラー+蓄電)で昼間電力を平準化、乾燥ピーク時の需要抑制に寄与。
省エネ・輸出・6次化に関連する補助・融資は、“成果(省エネ率・新売上)の数値計画”まで落として申請。
MRL・ポジティブリストを市場別に整理し、使用資材と収穫前日数(PHI)を管理表で一元化。
残留検査・水質検査の証跡を英訳テンプレートで常備。
バルク・ティーバッグ・粉末など形態別の規格書を用意し、問い合わせへの初動を早める。
研修受け入れ(短期)→シーズン雇用(中期)→新規就農支援(長期)の**“階段”**を地域で用意。
地域工場・共同乾燥など設備のシェアで小規模生産者の参入障壁を下げる。
若い世代がやりたい直販・体験・デジタルを、上の世代の栽培・製茶の技と重ねる“縦の分業”。
気候、人手、コスト、市場、規制。どれか一つではなく同時多発で起きています。鍵は、
データで可視化(気象・生育・防除・コスト・販売)
標準化(作業・記録・品質)
分担と連携(人・設備・販路)
の三点を“畑→工場→市場”の一本線でつなぐこと。
お茶は、土地と人の記憶の産物です。違いをつくる畑と、違いを伝える言葉、そして続けられる仕組みが揃ったとき、一本の新茶はようやく未来に届きます。
次の季節に向けて、できることを一つずつ“設計”していきましょう。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part20~
同じお茶でもお湯の温度・時間・茶葉量で味は劇的に変わります。ここでは、家庭で再現しやすいレシピと、品種・蒸し加減の相性、冷茶&氷出しまでを一気に解説。保存と水のコツもまとめました。
目次
急須(細かい網がベター)・湯冷まし・湯呑み
お湯は一度沸騰→湯冷ましで温度調整。
カップを温めておくと香りが立ちます。
できれば軟水が相性◎(ミネラルの強い硬水は渋みが出やすい)
(茶葉量は1人分目安。お好みで微調整してください)
煎茶(浅蒸し):茶葉2–3g / お湯100ml / 70℃ / 60–90秒
→ うま味と清涼感のバランス。
煎茶(深蒸し):2–3g / 100ml / 65–75℃ / 30–45秒
→ 微粉が多いので短時間でやさしく注ぐ。
かぶせ茶:3g / 80–100ml / 60–70℃ / 60–90秒
→ まろやか。2煎目は少し熱めで短時間。
玉露:3g / 30–40ml / 50–60℃ / 90–120秒
→ とろりとした旨味。少量高濃度で楽しむ贅沢
ほうじ茶:2–3g / 130–150ml / 90–100℃ / 30–60秒
→ 香ばしさは高温×短時間で。
玄米茶:3g / 120ml / 80–90℃ / 30–60秒
二煎目のコツ:温度を10℃上げて時間は半分。香りがふわっと開きます。
やぶきた:万能。70℃前後で甘渋バランス。
さえみどり/あさつゆ:旨味系。**60–70℃**の低温が映える。
おくみどり:香り穏やか、深蒸し短時間がきれい。
在来・香気系:やや高温で立ち香を楽しむ。
水出し:茶葉10–15g/1Lを冷蔵庫で4–6時間。苦渋み少なめ、甘みすっきり。
氷出し:急須にたっぷりの氷+茶葉、ゆっくり溶けるのを待って少量ずつ。とろ甘の特別な一杯。
急冷:70℃で短時間抽出→グラスに氷へ直接注いで急冷。香り華やか✨
お湯が熱すぎて渋い → 湯冷ましを一回多く通す。
味が薄い → 茶葉を気持ち多めに、時間は変えずに。
粉っぽい(深蒸し)→ 短時間&静かに注ぐ。
2煎目が冴えない → 抽出後の茶葉を開けっ放しにしない(乾かさない)。
光・酸素・湿気・温度を避ける。
開封後は小分け&チャックをしっかり。
長期保管は未開封を冷凍→使用分だけ冷蔵/常温。出すときは結露対策で常温に戻してから開封。
煎茶 × 和菓子・塩むすび
深蒸し × 揚げ物・サンド
かぶせ/玉露 × チーズ・ナッツ(少量で)
ほうじ茶 × 焼菓子・チョコ・和スパイス料理
週末は品種違い飲み比べセットで小さなテイスティング会
平日は水出しボトルでデスクに常備。
季節の便りに合わせてレシピカードを入れ替えると続きます。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part19~
お茶は“畑の香り”をそのまま飲み物にしたもの。だからこそ、畑→摘採→製茶→仕上げの全部で香りが育ちます。この記事では、農家の一年を月ごとの段取りでたどりながら、現場で効くコツをまとめました。️
目次
整枝・剪定:翌春の芽数と摘みやすさを決める大事な工程。畝ごとに“高さ基準”を写真で固定
施肥(基肥):ゆっくり効くものを中心に。施肥量は前年収量・葉色・土壌データで見直し。
排水路・風対策:豪雨と強風は“香りの敵”。溝さらい、支柱、畝肩の補修を冬のうちに。
土壌チェック:pH・EC・有機物。お茶は酸性寄りが得意。データはロット名で保存
防霜ファン/散水/不織布の準備✅
萌芽確認:畝ごとに発芽ステージを見まわり、被覆(かぶせ)開始の合図に。
かぶせ茶/玉露の被覆:遮光で旨味(アミノ酸系)が育つ。
かぶせ茶:目安1〜3週間
玉露:目安3週間以上
被覆開始・終了日は必ず記録
摘採適期:基本は一心二葉〜三葉。**雨後は含水率↑**なので無理をしない。
生葉の扱い:圃場から速やかに工場へ。搬入票に時間・畝・被覆有無を記録。
製茶フロー(荒茶):
蒸し(浅蒸し/深蒸し)→ 2) 粗揉 → 3) 揉捻 → 4) 中揉 → 5) 精揉 → 6) 乾燥
深蒸しは粉化しやすい分、抽出は短めを想定。
歩留まりの目安:生葉4〜5kg → 荒茶1kg。受入ロットごとに記録し、畝別の改善に。
官能チェック:立ち香・滋味・後口。**“香りノート”**を作ると翌年が楽に
二番茶:品質重視なら刈遅れ回避。一番茶後のお礼肥で樹を休ませつつ回復。
病害虫の見回り:チャノコカクモンハマキ・ハダニ・カイガラムシなどは畝端・日当たり端から出やすい。
IPM(総合防除):被害葉の早期除去・捕殺・草生管理で圃場のバランスを保つ。
草管理:足元の通風と作業性が香りを守る。猛暑時は早朝・夕方作業で安全第一
仕上げ:荒茶の選別・整形で外観を整える。
合組(ブレンド):畝・時期違いを組み合わせ、香味の再現性を作る職人仕事。
火入れ:低温〜中温で水分・香りのチューニング。焙香は行き過ぎ注意、メモと小試験で詰める。
保存:遮光・低温・低湿・脱酸素。開封後は小分けが鉄則
収量(kg/10a)・荒茶歩留まり(%)
水分・葉温・被覆日数・摘採日
官能点(香・旨・渋・後口)
クレーム/返品ゼロ日数・EC/店頭のリピート率
→ 畝×時期×被覆で並べると改善点が見える
摘採が遅れて渋味増 → 畝別カレンダー+“試し摘み”で前倒し。
深蒸しで粉っぽい → 造粒の工夫/ふるい直し+抽出推奨レシピを同梱。
火入れムラ → 小ロット試験→官能記録→温度再設定。一度に結論を出さない。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part18~
日本の茶文化は長い歴史を持ち、今なお私たちの暮らしに根付いています。その背景には、四季折々の自然と向き合いながら、丁寧に茶葉を育ててきたお茶農家の存在があります。しかし、彼らの果たしている役割は「茶を育てる」だけではありません。お茶農家は、地域経済を支え、雇用を創出し、地域ブランドを形作る「経済的プレイヤー」としての顔も持っているのです。
目次
お茶の生産は、農村部において重要な基幹産業の一つです。とくに静岡、鹿児島、京都、三重などでは、茶業が地域経済の中核を担っており、生産・加工・流通・販売に関わる産業全体が一つの経済圏を形成しています。
年間収入の柱となる生産農家の存在
加工場や機械メーカー、資材業者などの関連産業への波及
地域自治体の税収・補助金活用にも寄与
このように、お茶農家は一地域の「経済基盤」の一部を形成する不可欠な存在です。
お茶農家では、収穫期や加工期に多くの人手が必要とされるため、地域におけるパート雇用・短期就労の機会を生み出しています。高齢者や主婦層、学生など、多様な層が関わることができ、地域の生活と経済に潤いを与えています。
また、6次産業化を進める農家では、製造・販売スタッフ、観光ガイド、カフェ運営など、農業以外の職域も生まれており、地元の若者や移住者の雇用の場としても注目されています。
地域独自の気候や品種、製法を活かした「ブランド茶」の存在は、地域の経済力を高める武器になります。
宇治茶、八女茶、知覧茶、狭山茶などのブランドが高価格帯を維持
高品質・無農薬・オーガニックなどの付加価値が、国内外市場で評価
観光商品(お土産・体験・カフェ)としての経済波及効果
こうしたブランド力は、観光客誘致や移住促進にもつながり、経済的効果はお茶農家にとどまらず、地域全体に波及します。
日本茶の輸出量は近年増加傾向にあり、特に北米・欧州・アジアで健康志向の高まりとともに需要が拡大しています。
抹茶やほうじ茶が人気商品に
輸出による外貨獲得と農家の収益多様化
輸出に適した生産体制整備や認証取得が新たな経済活動を喚起
このようなグローバル展開も、お茶農家の経済的役割を国際レベルで拡張しています。
お茶農家は単なる生産者ではなく、「地域を再生させる主体」としての可能性を秘めています。茶畑を中心としたエコツーリズム、里山保全活動、福祉連携など、社会的意義と経済的価値の両立が実現可能な分野として注目されつつあります。
茶農家×観光=持続可能な観光経済
茶農家×福祉=地域福祉の新しいモデル
茶農家×教育=地域学習の場としての茶畑
私たちが日々楽しむ一杯のお茶。その背後には、お茶農家の労働と工夫、そして地域経済を支える静かで確かな営みがあります。
お茶農家の経済的役割は、「地方創生」のキーワードそのものです。今こそ、農業を支える視点から、地域経済を見直すことが求められているのかもしれません。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part17~
ということで、お茶農家における「多様化」の現在と可能性を、事例とともに深く探ります。
かつて「お茶農家」といえば、収穫から加工・販売までを一貫して行う専業農家が中心でした。しかし今、その姿は大きく変わりつつあります。気候変動、消費者の嗜好変化、流通の変化など、さまざまな要因に対応するため、お茶農家は生産のみにとどまらず、多様な形で事業の幅を広げ始めています。
目次
少子高齢化や茶の消費量減少を背景に、お茶農家の多くが「茶以外の作物栽培」や「茶加工品開発」に取り組んでいます。
例:柚子や梅などの果樹栽培との兼業
同じ山間地で育つ作物を組み合わせることで、季節ごとの収益バランスを取る工夫が見られます。
例:紅茶やフレーバーティーの製造
伝統的な緑茶だけでなく、紅茶やほうじ茶、ハーブとブレンドしたオリジナルティーを製造することで、新しい顧客層を獲得しています。
かつては市場や卸に出荷するのが主流だった茶農家も、近年では「6次産業化」により、自らブランドを立ち上げ、加工・販売まで行う例が増えています。
オンライン販売の充実
SNSを活用して全国の消費者とつながり、自社ECサイトや通販プラットフォームを通じてダイレクトに販売。
サブスクリプション形式の導入
月替りでお茶を届ける「定期便」は、顧客との継続的な関係を生み、収益の安定にもつながります。
茶畑の美しさや茶作り体験を活かし、観光や教育の分野へ進出する動きもあります。
グリーンツーリズムの受け入れ
茶摘み体験や手揉み体験、テラスカフェの併設など、訪れる人に「体験」と「物語」を提供する農園が増えています。
外国人観光客向けツアー
海外からの観光客にとって、日本茶文化は魅力的な体験価値。英語対応や農家民泊との連携も進んでいます。
お茶農家の多様化は、地域の福祉や教育、環境保全とも連動しています。
障がい者の就労支援との連携
茶摘みや袋詰め作業などを通じ、地域福祉との協働が行われています。
里山保全活動としての茶栽培
茶畑の維持は、斜面崩壊の防止や生物多様性の確保にも貢献しており、環境保全型農業としての意義も見直されています。
「お茶農家の多様化」とは、単に副業を持つことではありません。それは、自分たちの土地、文化、技術を多角的に活かし、変化に対応する柔軟な姿勢の表れです。お茶はもはや飲み物だけではなく、人を集め、体験を提供し、地域と未来をつなぐ存在になりつつあります。
お茶農家が生み出すのは、「一杯のお茶」だけではなく、「新しい暮らしのかたち」なのです。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part16~
ということで、茶畑の香りが持つ意味、農家にとっての精神的価値、そして暮らしへの影響について、静かに深く掘り下げます。
お茶の味や色は語られても、「香り」に焦点を当てた話は意外に少ないかもしれません。しかし、お茶農家にとって最も五感に訴えるのは、茶畑を吹き抜ける風の香りかもしれません。それは単なる植物の匂いではなく、**季節・時間・生命の営みを内包した“香りの風景”**なのです。
お茶の葉は、**揮発性香気成分(テアニン、メチル化合物など)**を多く含んでいます。とくに新芽の出る春先、朝露とともに茶畑を歩くと、青くて甘く、そしてどこか清々しい香りが鼻を満たします。
朝日が差し込む瞬間、しっとりと立ち上がる“若葉の香”
摘み取り直前の新芽から漂う“緑の密”のような香気
これらは、天気・風・葉の状態によって毎日異なり、まさに**「一期一会の香り」**として農家の心を包み込みます。
農家は、香りから茶葉の状態を直感的に読み取ります。
「今日はちょっと湿気が強くて葉が重いな」
「この畝の品種は、雨上がりが特に芳しい」
経験を積んだ農家ほど、視覚よりも嗅覚で変化を感じ取ると言われます。**香りこそが、茶の“生きている証”**なのです。
茶畑の香りは、農作業の合間にふっと心を和らげてくれる存在です。朝露の時間帯、摘採のあとの夕暮れ時、ふとした瞬間に漂う香りが、自然と一体になっている感覚をもたらします。
季節の変化に敏感になれる
無心になって作業に没頭できる
心が乱れていても、香りに触れるとスッと整う
香りは、**お茶農家にとっての“天然のセラピー”**なのです。
この茶畑の香りを、単なる「農業の副産物」ではなく、暮らしの中の価値として位置づけ直す動きも出ています。
茶葉を焙煎する香りを活かした観光農園や茶室体験
フレグランス商品やアロマオイルへの応用
精神衛生に効果がある“緑茶香気療法”の研究
香りは、日本文化の“感性”としての茶業を象徴する要素としても期待されています。
茶畑の香りは、風の中に溶け込んだ自然からのメッセージであり、農家が日々受け取る“見えないご褒美”です。それは、働く人の心を癒し、文化としての誇りを呼び覚まし、やがて消費者の食卓へと香りごと届けられます。
お茶は、味だけではなく、「香り」をもって人の心に寄り添うもの。ぜひ、次にお茶を飲むときには、その香りに、育った畑の風景と農家の想いを重ねてみてください。
