-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
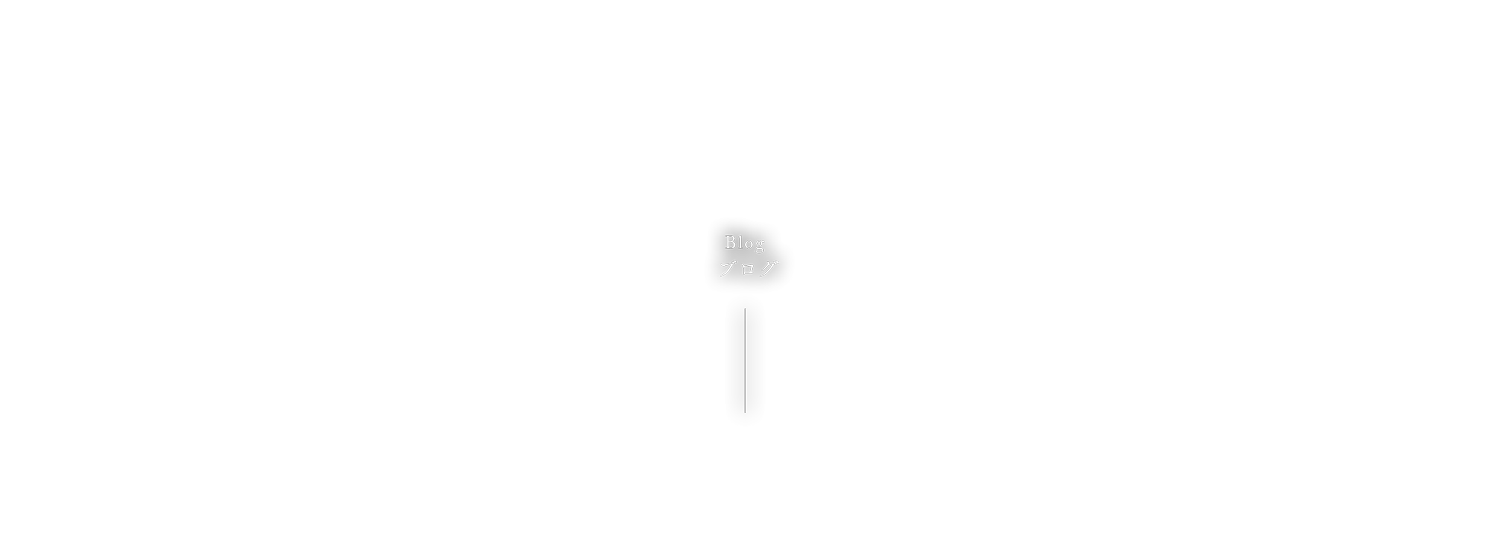
皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part17~
ということで、お茶農家における「多様化」の現在と可能性を、事例とともに深く探ります。
かつて「お茶農家」といえば、収穫から加工・販売までを一貫して行う専業農家が中心でした。しかし今、その姿は大きく変わりつつあります。気候変動、消費者の嗜好変化、流通の変化など、さまざまな要因に対応するため、お茶農家は生産のみにとどまらず、多様な形で事業の幅を広げ始めています。
目次
少子高齢化や茶の消費量減少を背景に、お茶農家の多くが「茶以外の作物栽培」や「茶加工品開発」に取り組んでいます。
例:柚子や梅などの果樹栽培との兼業
同じ山間地で育つ作物を組み合わせることで、季節ごとの収益バランスを取る工夫が見られます。
例:紅茶やフレーバーティーの製造
伝統的な緑茶だけでなく、紅茶やほうじ茶、ハーブとブレンドしたオリジナルティーを製造することで、新しい顧客層を獲得しています。
かつては市場や卸に出荷するのが主流だった茶農家も、近年では「6次産業化」により、自らブランドを立ち上げ、加工・販売まで行う例が増えています。
オンライン販売の充実
SNSを活用して全国の消費者とつながり、自社ECサイトや通販プラットフォームを通じてダイレクトに販売。
サブスクリプション形式の導入
月替りでお茶を届ける「定期便」は、顧客との継続的な関係を生み、収益の安定にもつながります。
茶畑の美しさや茶作り体験を活かし、観光や教育の分野へ進出する動きもあります。
グリーンツーリズムの受け入れ
茶摘み体験や手揉み体験、テラスカフェの併設など、訪れる人に「体験」と「物語」を提供する農園が増えています。
外国人観光客向けツアー
海外からの観光客にとって、日本茶文化は魅力的な体験価値。英語対応や農家民泊との連携も進んでいます。
お茶農家の多様化は、地域の福祉や教育、環境保全とも連動しています。
障がい者の就労支援との連携
茶摘みや袋詰め作業などを通じ、地域福祉との協働が行われています。
里山保全活動としての茶栽培
茶畑の維持は、斜面崩壊の防止や生物多様性の確保にも貢献しており、環境保全型農業としての意義も見直されています。
「お茶農家の多様化」とは、単に副業を持つことではありません。それは、自分たちの土地、文化、技術を多角的に活かし、変化に対応する柔軟な姿勢の表れです。お茶はもはや飲み物だけではなく、人を集め、体験を提供し、地域と未来をつなぐ存在になりつつあります。
お茶農家が生み出すのは、「一杯のお茶」だけではなく、「新しい暮らしのかたち」なのです。
