-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
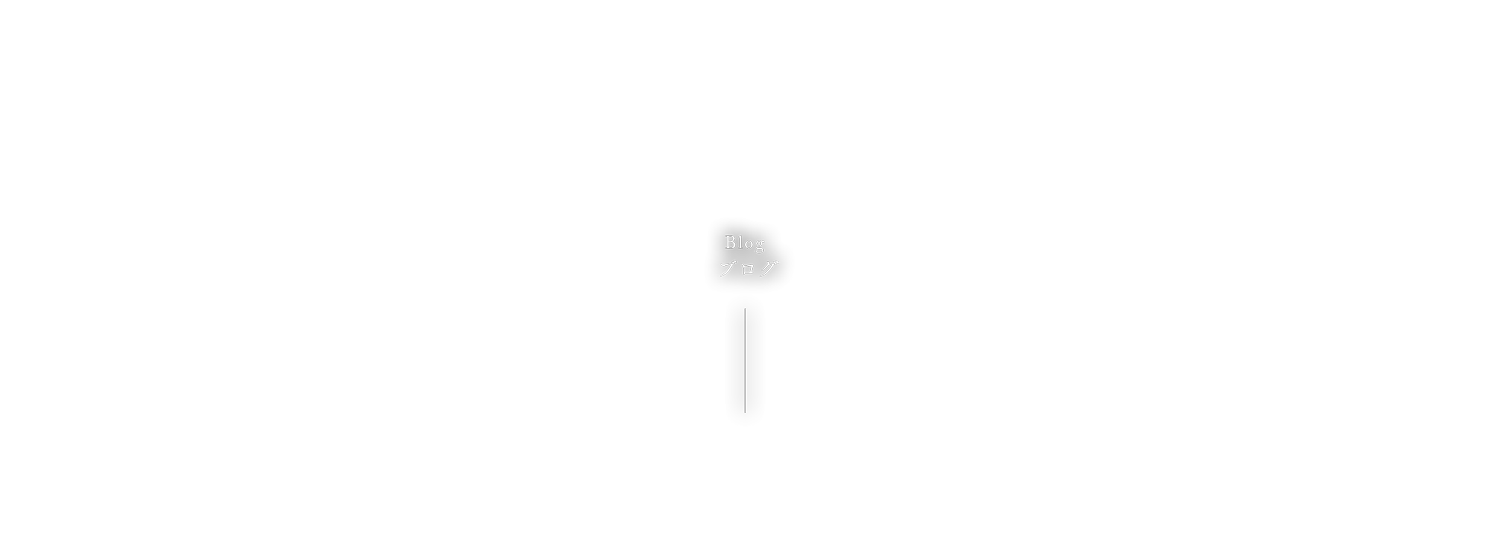
皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
~“茶の価値”~
現代のお茶農家は、かつてない変化の波の中にいます。
家庭で急須を使う人が減り、飲み物はペットボトルへ。
市場は大きくなったのに、農家の収益は厳しい。
さらに後継者不足、気候変動、肥料高騰…。
課題は山積みです。😥🌿
でもそれでも、お茶には価値がある。
そして茶農家には、未来へつなぐ力があります。🔥🍵
ペットボトル茶は、茶の消費を大きく広げました。
いつでもどこでも飲める。
しかし、製品は大量生産・大量流通。
農家は価格競争に巻き込まれやすくなります。📉
その中で重要になるのは、
契約栽培
品質規格
安定供給
農家は“安定した生産体制”を作ることで価値を出していきます。🏭🌿
健康志向の高まりで、日本茶は海外でも注目されています。
抹茶、煎茶、ほうじ茶…。
飲料としてだけでなく、スイーツや料理にも使われます。🍰✨
農家にとって海外市場は、新しい可能性です。
ただし、輸出は品質管理や認証、物流など新しいハードルもあります。📦🧾
後継者不足は深刻。
でも逆に言えば、今は新しい技術で農業を変えられる時代です。
ドローン防除
センサーで土壌管理
省力化機械
直販EC
茶農家は、伝統とテクノロジーを融合させて未来へ進めます。🚀🌿
お茶は単なる飲料ではありません。
香り、季節、もてなし、心を整える時間。
こうした文化価値があるから、茶は続いてきた。🍵✨
現代の茶農家は、味だけでなく文化も守る担い手です。🙏
薬から文化へ、庶民の飲み物へ、産業へ、そして現代の挑戦へ。
お茶農家の発展の歴史は、変化に適応しながら価値を作り続けた物語です。
そしてその物語は、まだ続いています。🍵✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
~茶農家は“産業”~
明治以降、日本は近代国家として急速に変化します。
その中で茶は、国内の嗜好品であると同時に、外貨を稼ぐ輸出産品としても大きな役割を担います。🌍💴
お茶農家の発展の歴史は、ここで一気に“産業化”していきます。🔥
明治期、日本は外貨を得るために輸出産品を必要としていました。
茶はその中でも重要な存在になります。
海外に向けて大量に供給するため、
生産量の増加
品質の均一化
加工の標準化
が求められました。📈
これにより茶農家は、単に“地域の作物”を作るのではなく、
“市場に合わせた生産”を意識するようになります。
ここで農業の考え方が変わったのです。🧠✨
茶は品種によって香りや旨味が変わります。
近代以降、品種改良が進むことで、
収量が増える
病害虫に強い
品質が安定する
などの変化が起きます。🌱✨
農家にとっては、
「良い芽を取る」だけでなく
「どの品種を植えるか」
が経営戦略になります。📊
茶農家は、ここで“技術型農業”としての色が強まっていきます。🔥
茶づくりは手作業が多い。
しかし需要が増えると、人手だけでは追いつきません。
そこで機械化が進みます。
摘採機(刈り取り)
蒸し機
揉捻機
乾燥機
これにより生産効率が上がり、茶農家は規模拡大が可能になります。📈
一方で、機械化は投資が必要。
資金計画や設備管理が重要になり、茶農家は“経営者”としての側面も強めていきます。💴🏭
戦後、日本の暮らしが安定すると、家庭でお茶を飲む習慣がさらに定着します。
急須で淹れる緑茶は“日本の家庭の味”になり、茶農家の需要は安定します。🍵✨
ここで茶農家は、地域の産業としてさらに成熟していきます。🌿
輸出、品種改良、機械化。
これらの波が茶農家を変え、技術と経営を伴う産業へ育てました。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
~産地の誕生と庶民の茶🍵~
お茶が寺院や武家の文化として広がった後、次に訪れる大きな転換点は「庶民化」です。
お茶が特別なものから、毎日の暮らしの中の飲み物へ。
この変化が起きたとき、初めて“茶農家”が職業として成立し、産地が生まれ、流通が整い、地域が茶で生きる時代が始まります。🌿🍵✨
近世における茶の普及と産地形成、そして茶農家の暮らしがどう形づくられたかを追います。📚
江戸時代、都市が発展し、人口が増え、商いが活発になる中で、庶民の生活にも“茶を飲む習慣”が根づいていきます。
それまでは高級品だった茶が、加工と流通の整備により、手が届く存在になっていきました。📈
茶は、
朝の目覚め☀️
食後の一服🍚
来客のおもてなし🏠
仕事の合間の休憩🛠️
といった生活の節目に入り込みます。
この“日常化”が、茶農家の市場を広げました。🌿✨
茶は、どこでも同じように育つわけではありません。
霧が出やすい山間部、昼夜の寒暖差、土壌の性質、水はけ…。
こうした条件が茶の香りと旨味を決めます。🍃✨
そのため、産地は自然に選別されていきます。
「この土地の茶はうまい」
「この地域は芽が柔らかい」
そうした評価が積み重なり、産地が形成されました。🏞️🍵
農家にとっては、
“茶が育ちやすい土地=生きる道がある土地”
でもあります。
お茶は換金作物としての価値が高く、農家の生活を安定させる力を持ちました。💴🌿
この時代の茶農家は、栽培だけでなく加工まで担うことが多いです。
摘採(芽を摘む)✋
蒸す🔥
揉む🧤
乾燥させる🌬️
この工程は、家族総出の仕事。
茶づくりの季節は、村の空気が変わるほど忙しくなります。😅
しかしその忙しさは、同時に“稼ぎ時”でもあります。
茶は保存が効き、商品として売れる。
茶農家は、農産物を「加工して価値を上げる」先進的な農業だったとも言えます。🌿📈✨
茶が日常になると、流通が重要になります。
街の需要に応えるために、茶問屋や行商が活躍し、農家と都市が結びつきます。🤝
農家は茶を作り、問屋が集荷し、加工や仕上げを行い、都市へ流す。
この分業が進むことで、茶農家は生産に集中できるようになります。📦🚚
ここで茶は“地域の産業”として強くなる。
農家は茶を作り続けることで地域のブランドが育つ。
ブランドが育てば価格が安定する。
この循環が、茶農家の発展を支えました。🍵✨
江戸期に茶が日常化し、産地が形成され、流通が整った。
このとき茶農家は職業として成立し、地域の暮らしを支える存在になりました。🌿✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
~「一杯の茶」~
お茶農家の歴史は、単なる農業の歴史ではありません。
それは「人の心を整える文化」と「地域の暮らしを支える産業」が、長い時間をかけて育った物語です。🍵✨
今、私たちが何気なく飲むお茶も、昔は特別な存在でした。高価で貴重で、場合によっては薬のように扱われた時代もあります。🌿🧠
お茶が日本に根づいていく“はじまり”と、お茶農家という存在が形になっていく前段階——寺院・貴族・武家が茶を必要とした時代を、歴史として丁寧にたどります。📚🍵
お茶の起源は中国にあり、日本へは遣唐使や留学僧などを通じて伝わったとされます。
この時代の茶は、今のような「飲み物」というよりも、身体を整える“薬”や“養生”に近い存在でした。🍵🧘♂️
僧侶たちが座禅や修行の合間に眠気を払うため、心身を整えるために茶を活用したことは、茶文化の大きな出発点です。
つまり日本の茶は、最初から「心と身体を整える文化」として入ってきたんです。🙏🌿
ここで重要なのは、茶を飲むためには“葉”が必要だということ。
茶が飲まれるようになれば、茶葉を育てる人が必要になる。
この需要が、のちの茶農家へとつながる土台になります。🏞️🍃
初期の日本では、茶は主に寺院や貴族社会の中で扱われました。
寺院は学問の中心でもあり、植物の栽培や薬草の知識を持っていました。
茶の栽培は簡単ではありません。気候、土壌、日照、管理…。
つまり、茶を育てるには“知”と“経験”が必要。寺院はそれを実践できる場所だったのです。🧠🌱
このころの茶の栽培は、現在のような広い農園ではなく、
寺院の敷地や周辺の山里に点在する形が多かったと考えられます。🌳🍃
それでも、茶樹を植え、芽を摘み、加工し、保存し、供給する。
ここに「茶を生産する」という営みが芽生えました。🌿✨
時代が進むと、茶は武家にも広がります。
戦乱の世では、心を落ち着かせる時間は貴重です。
茶を飲むことは、単なる嗜好ではなく、精神性や礼法を伴う文化になっていきます。🍵🧘♂️
やがて“闘茶”などの文化が生まれ、茶は一種の娯楽としても広がります。
ここで重要なのは、茶の需要が増えること。
需要が増えれば、供給が必要になる。
供給が増えれば、栽培が広がる。
茶農家の発展は、文化の発展とセットなのです。📈🍃
茶は、摘んだ葉をそのまま飲むわけではありません。
蒸す、揉む、乾燥させる…。
加工があって初めて“茶”になります。🔥🌿
つまり茶農家の歴史には、栽培だけでなく加工の工夫が必ず絡みます。
初期の茶づくりは、手作業で少量ずつ。
でもこの小さな積み重ねが、のちの大量生産と産地形成につながります。🧤✨
この段階では、まだ「茶農家」というよりも「茶を育て、茶を作る人々」が存在し始めた時代。
しかし確かに、茶産業の芽はここで育っていました。🌱🍵
お茶が薬として入り、寺院で育ち、武家に広がり、加工技術が芽生えた。
お茶農家の発展の歴史は、文化が先にあり、それを支える生産が後から広がった物語です。🌿✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part30~
年末は、一年を振り返ると同時に、
新しい年に向けた目標や想いを考える大切な時期でもあります🍃
畑が静かな表情を見せるこの季節、
これまでのお茶づくりを思い返しながら、
「来年はどんなお茶をお届けしたいか」
そんなことを考える時間が増えてきました。
お茶づくりは、
一朝一夕で結果が出るものではありません。
天候や気温、自然の変化に向き合いながら、
その時々の茶の木の状態を見極め、
丁寧に手をかけていくことが大切だと考えています。
派手なことはできませんが、
日々の管理や手入れを怠らず、
茶畑としっかり向き合うこと。
それが、安心して飲んでいただけるお茶につながると信じています🍵✨
剪定や施肥、畑の環境づくりなど、
お茶づくりには多くの工程があります。
どれも目立つ作業ではありませんが、
一つひとつを丁寧に積み重ねていくことで、
お茶の味や香りが少しずつ形になっていきます😊
「この作業が、次の一杯につながる」
そんな気持ちで、
日々の仕事に向き合っています。
これからも、
ご家庭でほっと一息つく時間や、
大切な方と過ごすひとときに、
寄り添えるお茶でありたいと願っています。
安心して飲んでいただけること、
そして「おいしい」と感じていただけること。
その両方を大切にしながら、
お茶づくりを続けてまいります🌱
新しい年も、
変わらぬ想いでお茶づくりに向き合い、
一杯一杯に心を込めてお届けしていきます。
これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、
次の一年も、
より良いお茶づくりを目指して歩んでまいります🍵✨
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part29~
12月は、一年間のお茶づくりを振り返る大切な時期です。
畑の景色も静かになり、
一年の出来事をゆっくり思い返す季節を迎えました❄️
春の芽吹きから始まり、
新茶の収穫、夏の管理、
そして秋を越えて冬へ。
お茶づくりは、一年を通して続く仕事です。
お茶づくりは、
天候や気温の変化に大きく左右されます。
思うように天気が安定しなかった日もあれば、
恵まれた条件の中で作業が進んだ時期もありました。
自然相手の仕事だからこそ、
毎年同じようにはいかず、
その年ごとに違った判断や対応が求められます🍃
無事に収穫を終えられたことに、
あらためて感謝の気持ちを感じています。
一年を通して、
うまくいったこともあれば、
「もっとこうすればよかった」と感じる場面もあります。
そうした経験をそのままにせず、
一つひとつ振り返り、
次の栽培に活かしていくことが大切だと考えています😊
少しずつでも改善を重ねることで、
より良いお茶づくりにつながっていくと信じています。
日々の作業では、
お客様に「おいしい」と言っていただける一杯を思い浮かべながら、
畑と向き合ってきました。
派手な作業ではありませんが、
剪定や施肥、日々の管理など、
すべての工程が味づくりにつながっています。
その積み重ねが、
皆さまのもとに届くお茶になっていると思うと、
大きなやりがいを感じます✨
一年を通して、
お茶を手に取ってくださった皆さま、
応援してくださった皆さまに、
心より感謝申し上げます。
皆さまの存在が、
お茶づくりを続けていく大きな励みになっています😊
年末のこの時期は、
次の一年に向けて気持ちを整える時間でもあります。
これからも、
一つひとつの作業を大切にしながら、
誠実なお茶づくりを続けてまいります。
新しい年も、
皆さまに喜んでいただけるお茶をお届けできるよう、
準備を進めてまいります🍃
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします🍵✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part28~
お茶づくりは、
新茶の収穫時期だけが大切なのではありません。
実は、12月から冬にかけて行う手入れが、
その年のお茶の品質を大きく左右します🍃
目立つ作業ではありませんが、
この時期の管理こそが、
おいしいお茶づくりの土台となっています。
冬のお茶畑では、
剪定や施肥、畑の環境整備など、
寒い時期ならではの作業を行います。
・茶の木の状態を見ながら行う剪定
・来春の芽吹きを支えるための施肥
・畑全体の環境を整える管理
これらの作業は、
すぐに目に見える結果が出るものではありません。
しかし、茶の木の健康を保ち、
安定した生育につながる大切な工程です😊
冬の間、
茶の木は寒さの中でしっかりと休み、
春に向けて力を蓄えています。
この時期に無理をさせず、
適切な手入れを行うことで、
春にはそろった芽が育ち、
香りと旨みのあるお茶へとつながります🍵✨
冬の管理は、
茶の木と向き合いながら、
その声を聞くような時間でもあります。
おいしいお茶は、
派手な作業から生まれるものではありません。
日々の畑管理や、
季節に合わせた手入れの積み重ねが、
最終的な味や香りの違いとなって表れます。
「冬にどれだけ丁寧に向き合ったか」
その積み重ねが、
一杯のお茶の味を支えていると感じています😊
冬の畑は静かですが、
その中では、
次の新茶に向けた準備が着実に進んでいます。
寒い季節の作業は決して楽ではありませんが、
春に芽吹く茶の木を思い描きながら、
一つひとつの作業に向き合っています🍵
これからも、
冬の手入れを大切にしながら、
茶の木の健康と品質を守ってまいります。
見えない季節の積み重ねが、
皆さまのもとへ届く、
おいしい一杯につながることを願って🍵😊
春の新茶を、
どうぞ楽しみにお待ちください。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part27~
12月になると、お茶畑は静かな季節を迎えます。
青々としていた畑の景色も落ち着き、
一見すると作業が少ないように見えるかもしれません🍃
しかし実は、冬は次の新茶に向けた、とても大切な準備期間でもあります。
冬の寒さの中で、
茶の木はしっかりと休みながら、
春に芽吹くための力を蓄えています。
この「休む時間」があるからこそ、
春には元気な新芽が育ち、
香りと旨みのある新茶が生まれます✨
茶の木にとって冬は、
次の成長に向けた大切な充電期間なのです。
作業が少なく見える冬ですが、
実際には畑の状態を確認しながら、
細やかな管理を行っています。
・土の状態の確認
・茶の木の様子のチェック
・畑全体の環境管理
寒さや乾燥の影響を受けやすい時期だからこそ、
一つひとつ丁寧に目を配ることが大切です👀
この時期の管理次第で、
春の芽の揃い方や新茶の品質が大きく変わってきます。
冬の間に、
土や茶の木の状態を整えておくことは、
おいしいお茶づくりの土台になります。
目に見える成果はすぐには現れませんが、
この時期の積み重ねが、
春にしっかりと形になって表れてきます😊
「冬にどれだけ手をかけたか」
それが、新茶の香りや味わいにつながります。
静かな冬のお茶畑に立つと、
春に広がる新芽の景色を思い浮かべることがあります。
今は静かでも、
この畑から、
多くの方に楽しんでいただける一杯のお茶が生まれる。
そう思いながら、
日々の管理に向き合っています🍵
冬のお茶畑は、
目立つ季節ではありません。
それでも、
見えない季節の積み重ねこそが、
春の新茶のおいしさを支えています。
これからも、
一つひとつの作業を大切にしながら、
おいしいお茶づくりに取り組んでまいります😊
春の新茶を、どうぞ楽しみにお待ちください🍵✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part26~
11月は、お茶の木が冬眠へ向かう大切なタイミング。
日照時間が短くなり、朝露が増え、温度差が大きくなるこの季節、茶園では“冬支度の総仕上げ”が行われます✨
10月までに夏の疲れを癒した茶樹は、ここから冬の低温に備える準備を開始。
11月の過ごし方が、そのまま 来春の芽吹き・新茶の品質 に直結します。
今回は、11月の茶園の気候的特徴、必要な作業、肥培管理、霜対策、来年への布石など、プロ農家が行う本格的な茶園管理を3000字以上で解説します
11月は気温だけでなく、土壌・湿度・日照など、多くの環境が変化します。
平均気温が10〜15℃に
土壌温度が安定して下がり始める
朝露・夕露が多くなる
日照時間が短くなる
茶樹の成長速度が大幅に落ちる
茶の木は“常緑樹”ですが、冬は成長をほとんど止め、省エネモードになります。
そのため11月の管理は、冬越し対策の基盤となります❄️
秋冬仕立ては、茶園管理の中でも最も重要な作業のひとつです。
新芽を揃え、翌年の収穫量を安定させる
日当たり・風通しを改善
病害虫のリスクを下げる
樹勢を整え、無駄な枝の養分消費を防ぐ
特に、翌年の一番茶の品質を決めるのは“今の枝の整理”とも言われます。
刈高(かりだか)を均一にする
裏枝・徒長枝を丁寧に処理
日照の入り方を計算
茶株の“高さ”の調整
軽くしすぎず、重くしすぎないバランス
数センチの差が、来年の芽の量と質を左右します✨
11月の肥培(肥料管理)は「翌春の芽への投資」です。
秋肥は茶樹の“冬を乗り越える体力づくり”。
有機質肥料(油かす・堆肥)
緩効性肥料
ミネラル補給
有機肥料は分解に時間がかかるため、11月の段階で土壌に施すと、ちょうど春に効きます✨
秋は土づくりが最も効果的な季節。
pH調整(苦土石灰など)
土壌の団粒化
排水改善
有機物の投入
硬くなった土を改善し、根の伸びやすい環境を作ります。
気温が低くなっても油断は禁物。
カンザワハダニ
チャノホソガ
うどんこ病
葉の黄化
これらは越冬して翌年に被害を出すため、11月中にしっかりチェックしておく必要があります。
12月〜2月にかけて降りる霜は、茶園に大きなダメージを与えます。
点検
ベアリング交換
給油
自動制御確認
落葉清掃
霜が降りる直前に壊れると手遅れのため、11月に入念に点検します。
草刈りしすぎると地温が下がる
適度に草を残して保温
排水改善で霜害軽減
茶園の“温度管理”は、実は冬でも非常に重要です。
山間の茶園では、冬に近づくと野生動物の活動も変化します。
シカ
イノシシ
サル
これらの被害を防ぐための対策も11月に行います。
11月は派手な作業が少ない反面、すべてが翌年に直結します。
秋冬仕立て → 芽のそろい
秋肥 → 味の深み
病害虫対策 → 健康な芽
霜対策 → 春の守り
土づくり → 樹勢アップ
この全てが合わさり、翌年の「香り・うま味・水色」に影響します✨
茶の木は“1年で成長する作物”ではありません。
同じ茶株と向き合いながら、何十年と育て続ける作物です。
だからこそ、11月の細かな作業が、
翌年だけでなく 数年後の木の状態や収量にも影響 を与えます。
お茶農家にとって11月は、
派手ではないけれど一番「未来をつくる月」なのです✨
11月のお茶農家は、
冬支度
秋冬仕立て
土づくり
病害虫チェック
霜対策
環境整備
を行い、“来年のお茶の品質”を静かに仕込んでいく時期です。
茶園がゆっくり休むこの季節に、
農家は次の春の香りと旨みを思い浮かべながら、丁寧な管理を行っています✨

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part25~
11月のお茶農家は、比較的落ち着いた時期と思われがちです。
しかし実際には 「来年の新茶の品質を決める一番大事な時期」 と言っても過言ではありません。
立冬を迎え、朝晩は10℃以下になる日も増え、茶園は冬の眠りに向けてゆっくりと準備を始めています❄️
そんな11月の茶園では、秋冬仕立て、土づくり、病害虫の最終チェック、霜対策準備など、多くの重要作業が進められています。
ここでは、11月の茶園管理がなぜ大切なのか、どんな作業が行われるのか、来年の品質にどう影響するのかを、専門的かつ分かりやすく深掘りします✨
11月はお茶の木にとって “冬支度の段階” です。
日照時間が短くなる
朝露が増える
気温差が大きくなる
土壌温度が下がり始める
茶株の成長が緩やかになる
つまり「今の管理=来春に出る芽の質を左右する」ということ。
お茶農家の11月作業は、春を見据えた長期的な視点で進みます✨
11月の茶園の主役作業といえば、 “秋冬仕立て”。
これは来年の一番茶の芽が出やすいよう、枝葉を整える作業です。
放置すると
枝が込み合い、日当たりが悪くなる
新芽の出る位置がバラつく
収穫量が下がる
病気が発生しやすくなる
11月の段階で枝を整理しておくことで、
春の新芽の出る“スタートライン”が整います。
古い枝・枯れ枝の除去
混み合った枝を間引く
日当たりを良くするための上部調整
刈り落としで株を均一に仕上げる
この作業は技術の差が大きく出る部分。
数ミリの高さが翌春の芽出しに影響することもあるため、かなり繊細な仕立てが求められます✨
11月は肥料を与える“秋肥”の時期でもあります。
秋に肥料を与えることで
冬越しに必要な栄養を蓄える
根の生育を促し、春の芽の力を強くする
茶樹の活性を保つ
深根化による基盤作り
特に有機肥料を使う場合、分解に時間がかかるため、春に効かせるためには“11月”がベストです。
有機肥料(油かす・鶏糞・ぼかし肥など)
粒状化成肥料
堆肥のすき込み
土壌改良資材(ゼオライト・苦土石灰)
土壌分析に基づき、窒素・リン酸・カリの配合を調整する農家も増えています。
繁忙期と比べて発生は少ないものの、11月は“最後の見回り”の時期。
特に
チャノホソガ
カンザワハダニ
黄化現象
うどんこ病の初期症状
これらを放置すると、越冬して翌年に被害が広がります。
12月に入ると、地域によっては霜が降り始めます。
霜害は新芽が出る翌春に致命的な被害を与えるため、11月から準備を開始します。
防霜ファンの点検
給油・稼働試験
温度センサーの確認
茶園の風通しの調整
草刈りで地温低下を防ぐ
防霜ファンは、一番茶の品質を守る“茶園の守護神”とも言われる大切な設備です❄️
畝間の草刈り
排水路の整備
土の盛り直し
茶園周囲の片付け
冬の害獣対策
特に11月は“排水”が重要。
冬に雨が多い地域では、土壌が過湿状態になると根腐れが起きやすくなります。
お茶農家にとって11月は「静かだが最も重要な準備期間」。
まだ寒さの本番ではなく、茶の木も冬眠前の余力があるので、
株の整え
根の伸長
土壌改良
病気対策
が効率よく行えるのです。
人で言えば、冬に備える体力作り・ストレッチのような時期といえます
11月の茶園は、一見何も変化がないように見えて、裏では“来年の春の準備”が進んでいる大切な時期です。
秋冬仕立て
土づくり
病害虫チェック
防霜準備
排水改善
これらの積み重ねが、来年の一番茶の香り・うま味・品質につながります。
丁寧に整えた茶園は、春に必ず応えてくれる──
それが、お茶農家の11月の本質なのです✨
