-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
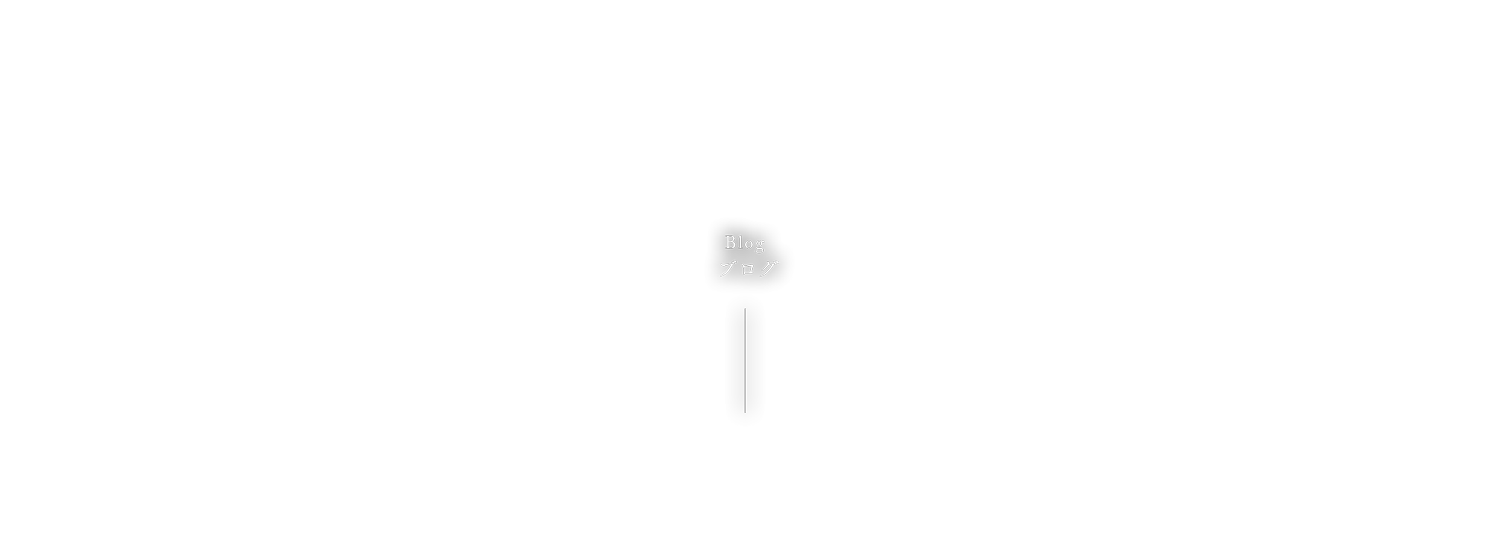
皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part24~
「選ばれ続ける」ためのブランド・商品・体験・環境・人の話。価格競争ではなく、価値競争へ。6次化(加工)×観光×デジタルを組み合わせ、ファンと一緒に育つ茶園を目指しましょう。
ストーリー軸:品種の来歴、標高、朝霧、被覆、家族の役割。
科学の裏付け:アミノ酸・カテキン・カフェイン等の簡易分析(外注OK)→味覚の理由を数値で示す。
写真と言葉:茶畑の陰影・雲海・露を切り取る。コピーは五感+具体で。「湯冷まし50℃、とろり甘旨」
フラッグシップ:単一畑・単一品種・年ごとにロット番号。限定性でファン化。
デイリー:ブレンドで味の安定を提供。定期便の軸に。
体験型:水出しボトルキット・ラテベース・茶スイーツ素材(抹茶・粉末ほうじ茶)。
ギフト:季節しおり・淹れ方カード・ペアリング案を同梱で“説明いらず”。
正面:品種/火入れ強弱/旨・渋・香のレーダー。
側面:抽出レシピ(温度・時間・湯量・二煎目)。
背面:畑座標・標高・収穫期・被覆の有無・ロットQR。
素材:アルミ蒸着+チャックで鮮度キープ。30g/80g/200gの使い切り設計。
小型焙煎機×二段火:低温で甘香→仕上げに高温で香り立ち。
真空パック・脱酸素剤:火入れ後の酸化スパイクを抑える。
粉末化:**微粒粉砕(超微粉)**は耐湿管理が命。シリカゲル+窒素置換で固結回避。
委託加工を賢く併用:品質基準とロット管理を明記したSLAを締結
新茶手摘み体験(5月):摘んで→蒸して→手揉み→試飲。オリジナル缶に封入してお土産へ。
朝もや茶会:日の出&雲海×一煎。写真コンテンツとしても最強
焙煎ワークショップ:自分の火入れでマイブレンドづくり。
カフェ併設:茶プリン・ほうじラテ・抹茶ソフトで客単価UP
安全配慮:刈払機・蒸し釜周辺は立入線/保険/熱中症対策を徹底
オンライン茶会:月1回、同じロットを飲みながら味を言語化。
茶畑オーナー制度:名前入り札&収穫ボーナス。農繁期ボランティア受け入れで人手も確保。
レビューの可視化:悪い声も改善実績とセットで公開=信頼貯金
お菓子屋さん:抹茶/ほうじ粉末の粒度・香気を試作セットで提案。
カフェ:水出し濃縮×ソーダ、ほうじ×ミルクフォームのドリンク開発。
酒蔵:緑茶酒・ほうじ茶梅酒でコラボ。季節限定はSNSで拡散しやすい
被覆資材の再利用率、ボイラ燃料の切替(LP→電化/木質)、製品当たりCO₂を開示。
生物多様性:畦の草花ベルトで天敵昆虫を呼ぶ。フェロモントラップで農薬低減。
雨水利用・太陽光:水出しラインのチラー電力を再エネに。
茶殻アップサイクル:消臭材・コンポスト・染色に活用♻️
猛暑&少雨:点滴灌水+マルチングで葉温を下げ、苦渋みの暴発を抑制。
春の遅霜:防霜ファン+散水氷結の複合。SMS一斉アラートで緊急招集
炭疽病・輪斑病:風通し(剪枝)と発病葉の早期除去。
人材:マニュアル動画化/技能マトリクスで“属人化”を溶かす。繁忙期は地域×学生バイトのハイブリッド。
EC:定期便(毎月/隔月)、季節限定、送料無料ライン、レビュー特典。
実店舗:試飲→即決の導線。0.5g×3種の飲み比べで「違いがわかる」を演出。
同梱物:淹れ方カード・ペアリング表・畑だよりで“箱を開けた瞬間から茶会”。
写真:逆光で透ける茶葉、注ぎ初めの“黄金の糸”。光の演出が命
歩留まり(荒茶→仕上げ%)、再焙煎率、返品率、鮮度在庫日数、定期便継続率。
イベントKPI:体験参加→EC登録→2ヶ月後購入の転換率。
CXスコア:「また買う/人に勧めたい」をアンケで数値化。改善はひとつずつ
打ち手:単一畑ロット化/火入れ二段化/水出しキット化/朝もや茶会/CO₂表示。
結果:定期便継続率**+18pt**、ギフト客単価**+27%、来園→EC登録+42%**。
学び:体験→言語化→データの循環がブランドを強くする。
小さな茶園でも、大きな物語を育てられます。鍵は、畑のリアルと科学の言葉、体験の楽しさと環境の誠実さを一本に束ねること。今日の一歩は、製品ラベルに“抽出レシピ&ロットQR”を足すだけでもOK。あなたのお茶は、きっともっと“語られる味”になります。

皆さんこんにちは!
有限会社お茶の山佐園の更新担当の中西です!
山佐園の茶話~part23~
茶樹の声に耳を澄まし、天気と対話し、工程を科学する。そんな“丁寧な当たり前”の積み重ねが、湯飲み一杯の感動に変わります。今日は、圃場管理→摘採→製茶→仕上げ→販売まで、一気通貫の“勝ち筋”を解説します。✨
園地の向き(アスペクト):東向きは朝露が早く乾き病気リスク低減。北風の当たり具合で芽伸びが変わる。
土作り:pH5.0〜5.6目安。**完熟堆肥+有機質(菜種粕・魚粉)**で団粒構造を育て、**根の“呼吸”**を守る。EC(電気伝導度)で施肥過多を見える化
品種設計:早生(やぶきた)×中生(おくみどり)×晩生(さえあかり)でリスクと収穫負荷を分散。被覆適性や萎凋向きもあらかじめ想定。
かん水・排水:極端な乾燥は旨味(アミノ酸)↓、過湿は根痛み→黄化。点滴チューブ+土壌水分センサーで「与えすぎない勇気」
ミニTIP:苗の定植は南北畝で光を均等に。終日西日の強い畝は被覆ネットで葉温を抑え、渋みの暴発を防ぐ️
剪定:深刈りは更新、浅刈りは収量維持。2〜3年の設計でローテーション。
整枝:摘採面をフラットに保つ=均一蒸しの土台。波打ちは粉砕・粉がれの原因。
被覆(玉露・かぶせ茶):遮光率・期間で旨味の伸びが変わる。直掛け→本簾へ段階的に。葉色・香の“変調”を観察
基準:一芯二葉(早取りは旨味↑・香り繊細/遅取りは香り濃いが渋味↑)。
時間帯:朝露が切れてから。露付きは蒸しムラ&粉砕の元。
機械設定:回転数・刃当たり・コンベア角度で粉砕率が激変。**“葉が泣く音”**がしたら刃圧高すぎ
ロス対策:コンテナの通気・保冷。摘み置き加熱を防ぐため、30分以内搬入を厳守
蒸し:浅蒸し(香り立ち&透明感)/深蒸し(濃度&まろみ)。芽の硬さ×葉厚×葉温で秒数を微調整。蒸しすぎは青臭消失&粉増、不足は渋味尖り。
粗揉:揉みこみは細胞をほぐし水分均一化。風量と温度で乾燥速度の曲線を描くイメージ。
中揉:線条を整え、過乾燥を避けて内部水分を中心へ移動。
精揉:光沢を出し、形を締める。ここでの手離れ感は香味安定のサイン✨
乾燥:水分4〜5%目標。水分計の校正を月1回。乾きムラは火香の付き方を不安定に。
センサー活用:排気湿度・排気温のログ化で、蒸しから乾燥までの“香味カーブ”を見える化
篩い分け:針状・粉・茎などパーツごとに。欠点除去=味の解像度UP。
火入れ(焙煎):低温長時間→甘香(あまか)、高温短時間→香ばしさ。二段火で奥行きを作る。
合組(ブレンド):畑違い・ロット違いを狙いの味に寄せる職人技。味覚ボキャブラリー(旨味・渋味・滋味・火香・青香)をチームで共通化️
青臭の過剰:蒸し不足→蒸し秒+5〜10/眠り葉混入→選葉強化
渋味尖り:摘採遅れ/高温乾燥→火入れ温度↓+時間↑
にごり出汁:粉の混入→ふるい強化/深蒸し過多→蒸し温度見直し
吸湿臭:保管温湿度×包装。脱酸素・低温倉庫で鮮度キープ❄️
煎茶:70℃・1分→甘旨、85℃・30秒→香強。二煎目の最適化も提案。
玉露:50℃・2分で旨味の海。
ほうじ茶:95℃・30秒、ミルク割りのレシピカードを同梱
水出し:冷蔵3〜4時間。カフェイン控えめ訴求で夏の主役
生育モニタ:葉温・土壌水分・日射量をクラウドで。
CO₂見える化:ボイラ燃料・電力使用量を製品当たりで表示→環境値をブランドに。
トレーサビリティQR:畑・品種・蒸し秒・火入れ温度を開示=信頼の源泉
季節便(新茶・夏の水出し・秋の焙じ・冬の玄米茶)
ペアリング提案(和菓子・チーズ・チョコ)
ティーバッグは“美味しい”を証明:ドリップ式や三角メッシュで抽出性↑
SNS:蒸気の立つ動画・茶葉の手触り・湯呑みの音——五感を伝える
お茶は畑→工程→言葉→体験の総合芸術。畑で整え、工程で磨き、言葉で届け、体験で定着させる。今日からできる一歩は、蒸し〜乾燥の排気ログをとって“自園の香味カーブ”をつくること。来年の新茶、きっと別格になりますよ。✨
